
学校でのスピーチ、職場でのスピーチ、就職活動でのスピーチ・・・
社会に出るとスピーチをする機会が増えていきます。
明日「1分間スピーチ頼むね」と言われても、そもそも1分間スピーチってどのくらい?という疑問が生まれますね。

ということでこの記事では
1分間スピーチの最適な文字数とスピード、構成方法を実際の例文とともに解説していきます。ぜひご活用ください。
1分間スピーチの文字数は基本「300文字」
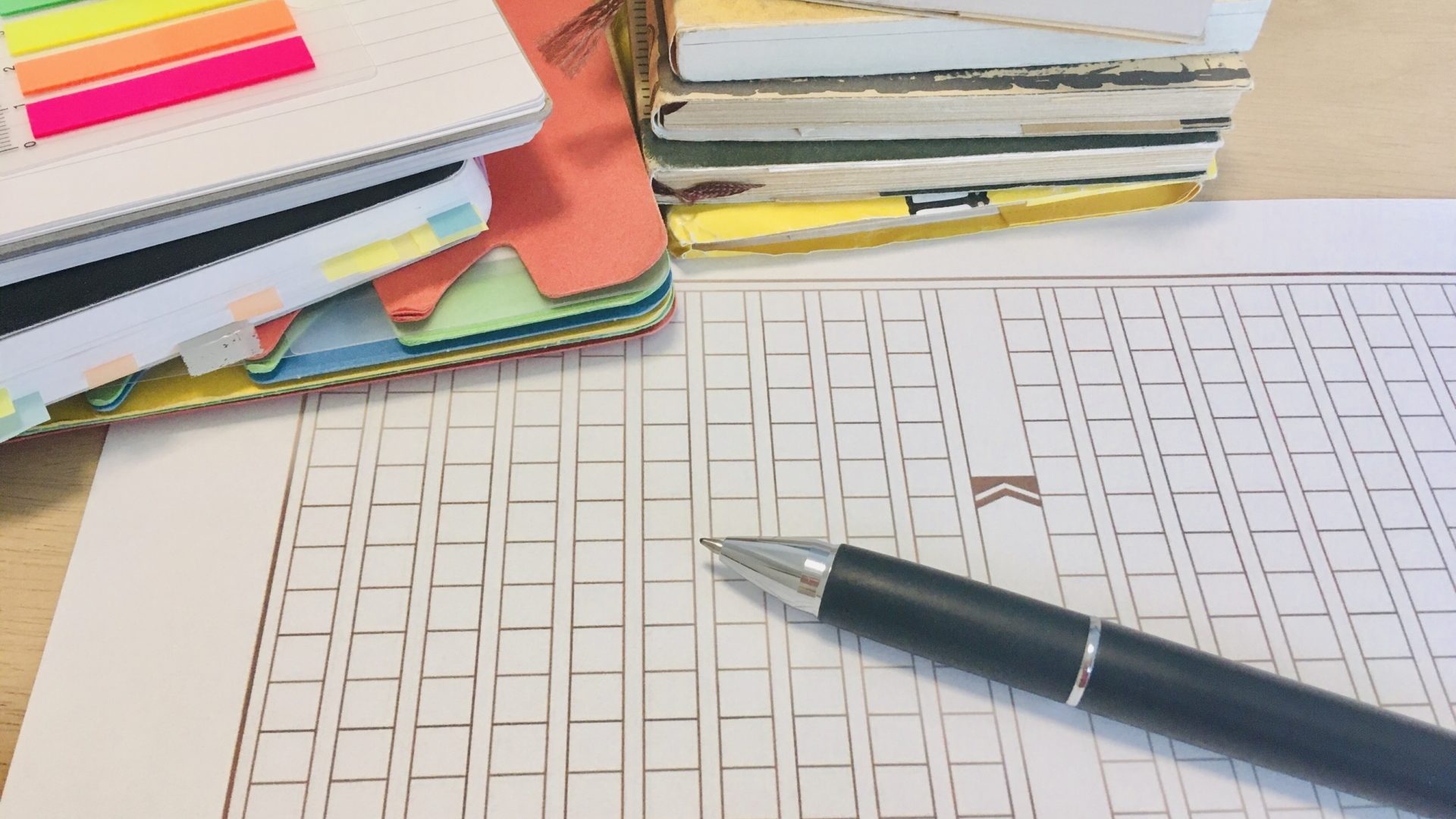
なぜ1分間スピーチは基本300文字なのか
結論からお話すると、一般的な速度でスピーチをすると
おおよそ「1分間で300文字」という文字数になります。
300文字とは作文用紙でいうと1枚に少し満たないぐらいの文字数です。
1分間で400文字や500文字を話そうとすると
どうしても早口になってしまい、聞き取りにくいスピーチになってしまいます。
反対に文字数が100文字など極端に少なくなると時間が余ったり
スピーチの内容が薄くなってしまいます。
| 1分 | 300文字 |
| 1分半 | 450文字 |
| 2分 | 600文字 |
| 2分半 | 750文字 |
| 3分 | 900文字 |
スピーチ作成時には文字数を計測してくれるツールを使うと便利です!
→「文字数をカウント」するために便利なツール5選
必ずしも300文字にこだわる必要はない
しかしながらこの300文字はあくまで目安です。
TPO(時・場所・目的)にて使い分ける必要があります。
例えば「高齢者の前でスピーチをするとき」や「低学年の子供たちの前でスピーチをするとき」は話すスピードをゆるやかにして考えてもらう間(ま)を意識的に作るべきです。
この場合は「220~250文字」程度で文章を構成するべきです。
また経営者や男性が多い講演会などで話すときには
比較的スピードをあげて「330文字~350文字」で文章を作ると聞き手に入りやすいでしょう。
- 1分間スピーチは300文字を基準にする
- 聞き手に合わせて文字数を調節する(高齢者施設や小学生→220~250文字 経営者や男性が多い講演会→330文字~350文字)
スピーチの適切なトークスピードとは

1分間スピーチのだいたいの文字数はわかりました。
ではスピーチをする上で適切なトークスピードにするためにはどうすればよいのでしょうか?
意識すべき注意点を2つご紹介します。
適切なスピードで話すためには「間抜け」に気をつける

「マヌケ!」というと何か人をバカにする表現に聞こえますが
スピーチでの「間抜け」とは人を揶揄するマヌケではなく、「間が抜けている間抜け」です。
営業で商品を説明するとき、電話で要件を伝えるとき、朝礼でスピーチをするとき
皆さんは意識的に間を作ることができていますか?
実際にそのような場面を録音して第三者目線で聞いてみるとよいです。
説明することに集中しすぎるあまり
「相手が理解する間や相手に質問をさせる間」がないことがわかると思います。
人には理解力の速い人遅い人、聞く能力に長けている人、そうではない人がいます。
こう話しているときにもスピードが速くてついていけない人、何を言ってるのか理解することが難しいという人は世の中に沢山います。
自分が発した言葉全てを理解してもらうことは難しいですが
全てを聞いてもらうことは出来るはずです。
人前で話す時はマヌケにならないよう間を意識して話してみましょう!
具体的には
句点「。」で1・2
読点「、」で1
ぐらいの間を作ることを心がけましょう。
- スピーチのマヌケ=間抜けに気をつける
- 句点「。」で1・2、読点「、」で1の沈黙の間を作る。
遅口言葉??口を大きくして話そう

まずは次の早口言葉を口に出してみてください。
「生麦生米生卵」
「隣の客はよく柿食う客だ」
噛まずに言えましたか?
…すいません、噛まずに言えたかどうかは今回は関係ありません。
口の動きに注目してもう一度言ってみて下さい。
「生麦生米生卵」
早口で話すときは口が小さく開くのがわかると思います。
スピーチで早くなってしまう原因は口の動きにあります。口を小さく開くことでスピードを上げて話すことが出来てしまうのです。
つまり、この逆の意識を持つことが大切になります。
早口言葉と逆で口を大きく開けることを意識することだけで、話すスピードはゆるやかになります。
スピーチをするときは出来るだけ口を大きくして話すことを意識してみてください。
- 口を大きく開けることを意識することだけで、話すスピードはゆるやかになる
ゆっくり話している人の真似をする

ゆっくり話ししている人の動画などを見て真似をすることがとても有効です。
今はYouTubeなどの動画共有サイトで簡単に無料で見れる時代です。
どんな人でもいいので「こうなりたい」というモデルを見つけて話し方の真似をしてみましょう。
話す間や仕草、目線のやり方などとても勉強になります。
1分間スピーチを作るために知っておくべきこと

さてここからは1分間スピーチの文章を作る上で気を付けるべきこと
そして、その文章構成を見ていきたいと思います。
スピーチは料理と同じ。内容はシンプルが一番伝わる。

突然ですがみなさんは料理をしますか?
料理にはレシピが存在します。
そのレシピには使用する具材や調味料などが細かく分量で書かれていることがほとんどだと思います。
決して美味しいからといってスパイスを大量にいれたりしては味が崩れてしまいますね。
いろんな具材や調味料を入れてもおいしくならない。味がぶつかり合って「なんだこの味・・・」と思ってしまいます。
スピーチも同じなのです。
「あれもこれも伝えたい!」と文章に詰め込みすぎないことが大切なんです。
1分間スピーチは300文字が目安と先ほどお話しました。
300文字というと作文用紙で1枚にも満たさないぐらいの文章です。
その文字数の中で伝えたいことを沢山詰め込みすぎると
聞き手は「結局何が言いたかったんだろう?」と疑問に思ってしまいます。
1分間スピーチは原則として「伝えたいことを1点に絞る」こと。
シンプルに伝えることと一番よいということです。
- スピーチは料理と同じ!具材や調味料を沢山入れると味がまとまらない。
- 1分間スピーチは原則として「伝えたいことを1点に絞る」こと。
起承転結は通用しない。1分間スピーチの構成
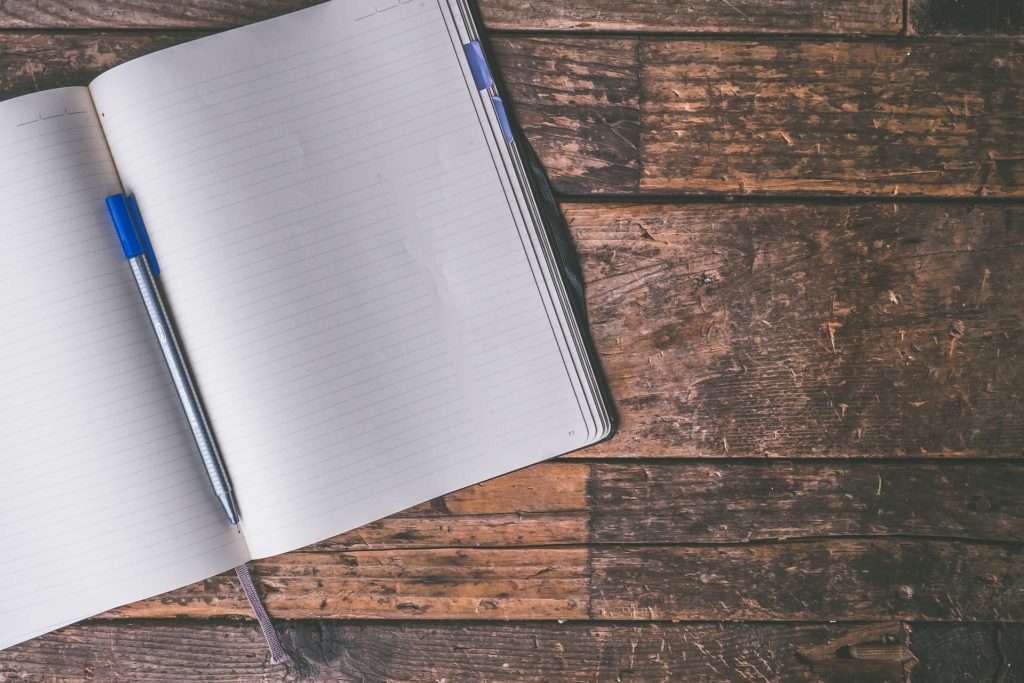
作文や文章といえば「起承転結」を盛り込むことが大切とよくいわれますね。
長いスピーチや作文などでは有効ですが、1分間スピーチで「起承転結」を盛り込むのは大変難しいです。
というのも1分間の目安である300文字の間で4つの展開を作るというのは不可能ですし、もし出来たとしても聞き手はついていけない内容になります。
そこで私は3段階構成を意識して作っています。具体的には
・投げかけ→データ(事実)→私見・まとめ
・経験→結果→私見・まとめ
この2パターンを活用します。細かい構成は「1分間スピーチの構成は?作り方を徹底解説」で解説しています。
実際の1分間スピーチの例文(カテゴリ別)
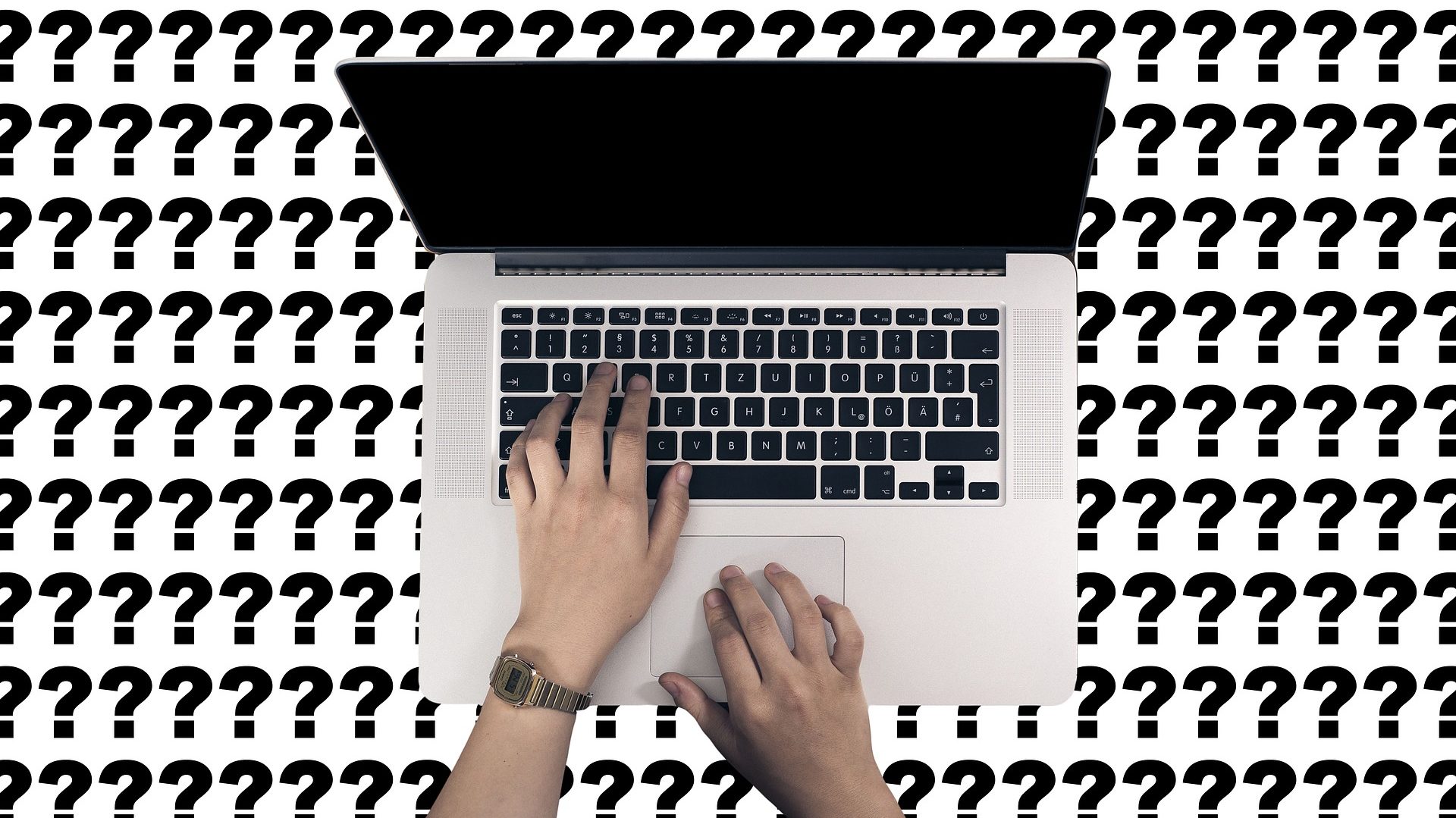

それでは実際の1分間スピーチスピーチの例文をカテゴリ毎にまとめました。
各々アレンジしてお使いください。
まとめ
1分間のスピーチにおいて、適切な文字数を把握することは重要です。一般的には250~300文字が目安とされていますが、具体的な内容や話し方によっても異なることを覚えておきましょう。
短すぎず長すぎず、聴衆の関心を引きつけるストーリーや要点の伝達ができる文字数を目指しましょう。スピーチの成功は、適切な言葉の使い方と時間の使い方にかかっています。練習と経験を重ねながら、自信を持ってスピーチに臨みましょう!以下がこの記事のおさらいです。
- 1分間スピーチは300文字を基準にする
- 聞き手に合わせて文字数を調節する(高齢者施設や小学生→220~250文字 経営者や男性が多い講演会→330文字~350文字)
- スピーチのマヌケ=間抜けに気をつける
- 句点「。」で1・2、読点「、」で1の沈黙の間を作る。
- 口を大きく開けることを意識することだけで、話すスピードはゆるやかになる
- スピーチは料理と同じ!具材や調味料を沢山入れると味がまとまらない。
- 1分間スピーチは原則として「伝えたいことを1点に絞る」こと。
筆者について

毎日更新!1分間スピーチの例文集の管理人
経歴:大学卒業→20代で5社を経験→専業ライター
20代で人事部や総務部などを経験し、現在はあらゆるスピーチのライターを専門として様々なサイトの運営に関わっています。



コメント